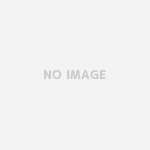「引越しするけど郵便物の転送の手続きはどうしたらいいの?」
「郵便物の転送っていつまでに手続きをしないといけないの?」
なんてあなたは思っていませんか?
転送手続きをしておけば、もし契約しているサービスの住所変更を忘れていても郵便物が引越し先に届くので安心です。
この記事では、
- いつまでに手続きをしたらいいのか
- どこで手続きをしたらいいのか
- 転送開始は手続きしてからどのくらいかかるのか
などについて詳しく解説します。
これを読めば、郵便物の転送手続きで困る事は無いでしょう。
引っ越しのためにある引越し業者に見積もりを取ったら73,300円でした。
高いんじゃないかと思って
あやうく31,300円も損するところだったんです。
複数の業者に見積もりを取ることで安い業者を見つけることができました。
見積もりの手間を省くなら「
利用時間は1分程度で利用料は無料になります。
SUUMOは一部上場企業のリクルートが運営しているサイトで、電話登録が不要で迷惑電話が来ないのも安心です。
引越し料金で損したくない方は是非こちらをご覧ください。
>>>あなたに合った最安値の引越し業者を調べてみる(無料)<<<
目次
- 1 郵便物転送の引越し手続き
- 2 郵便物転送の引越し手続きはどこでするの?
- 2.1 郵便局の窓口で転送手続き
- 2.2 転居届けのハガキを郵送する転送手続き
- 2.3 インターネットでの転送手続き
- 2.4 転送手続きに必要な書類等は?
- 2.5 いつまでに転送手続きはしたらいいの?
- 2.6 転送開始は手続きしてからどのくらいかかる?
- 2.7 転送手続きの経過は確認できるの?
- 2.8 どのくらいの期間転送してくれるの?
- 2.9 転送期間の延長ができるって本当?
- 2.10 転送期間の延長をせずに1年経過して、その後郵便物が旧住所地に届いたらどうなるの?
- 2.11 転送の取り消しはできるの?
- 2.12 転送先から再度転送したい時はどうしたら良いの?
- 2.13 転送手続きは土日祝日でも可能?
- 2.14 代理人の手続きは可能なの?
- 3 転居の事実確認について
- 4 さいごに
郵便物転送の引越し手続き

多くの人が言う「郵便物転送の引越し手続き」とは、日本郵便が行っている郵便物転送サービスの事です。
このサービスは、予め手続きを行っておけば、転居前の住所に届いた郵便物を転居先の住所に届けてくれます。
この転送サービスは届け出から1年間有効で、しかも無料です。
特に費用も掛からず手続きも簡単で、便利なサービスなのでやっておいた方が良いでしょう。
郵便物転送の引越し手続きはどこでするの?
郵便物転送の引越し手続きは
- 郵便局の窓口
- 転居届けのハガキの郵送
- 郵便局のホームページ
の3種類の方法で行えます。
郵便局の窓口で転送手続き
最寄りの郵便局の窓口に行って「引越ししたので郵便物の転送手続きをお願いしたい」と言えば、その場で手続きが行えます。
転居届けのハガキを郵送する転送手続き
郵便局に用意されている「転居届けのハガキ」に必要事項を記入して投函することで転送手続きを行えます。
インターネットでの転送手続き
郵便局が運営するホームページにインターネットを経由してアクセスする事で、パソコンやスマートフォンから転送手続きを行えます。
転送手続きに必要な書類等は?

転送手続きに必要な書類等は手続きの方法によって異なります。
それぞれの方法に分けて解説していきます。
郵便局の窓口で転送手続きの場合
運転免許証や保険証などの身分証明書、印鑑
郵送での転送手続き場合
転居届けのハガキ
インターネットでの転送手続き場合
連絡の取れるメールアドレス
いつまでに転送手続きはしたらいいの?

転居日の2週間前から、遅くとも1週間前には行いましょう。
郵便物の転送開始日は、手続き時に設定する事ができるので、引越し予定日が分かった後は早めに手続きを済ませておいても大丈夫です。
転送開始は手続きしてからどのくらいかかる?
転送開始は手続き後3日から1週間で手続きが完了します。
その為、できるだけ転居の1週間前には転送手続きを済ませておいた方が良いでしょう。
転送手続きの経過は確認できるの?
転送手続きの経過は、転送手続き時に入手できる転居届受付番号を持っていれば、その番号を使って郵便局のホームページから検索を行い進捗状況を確認できます。
何か手続きに問題が起こる事もあるので、転居届受付番号は転送手続きが完了するまでは手元に置いておいた方が良いでしょう。
どのくらいの期間転送してくれるの?

郵便物の転送手続きは転送開始日から1年間は、特に何もしなくても転送し続けてくれます。
転送期間の延長ができるって本当?
実は郵便物の転送手続きは更新が出来ます。更新すると郵便局側では再度転送手続きを行ったという事になり、再度転送開始日から1年間転送し続けてくれます。
そして、この更新は特に規定が無いので、何度でも転送手続きを更新する事が出来ます。
ですので、極端な話をすると、もし毎年更新を続ければ何十年も郵便物を転送し続けることも出来ます。
転送期間の延長をせずに1年経過して、その後郵便物が旧住所地に届いたらどうなるの?
この場合、郵便局が転居を確認していれば、宛先人不在として発送元に返送されます。
しかし、賃貸などで転居が確認されていないと、新しい入居者の元に届く事になります。
転送の取り消しはできるの?
転送サービスは取り消しの規定が無いので取り消す事は出来ません。
1年間時間が経過する迄は停止も解除も出来ません。
しかし、郵便局にお願いすれば取り消しが出来ることもあるそうなので、もし取り消したい方は郵便局に相談してみて下さい。
転送先から再度転送したい時はどうしたら良いの?

郵便物の転送サービス中に、引越しをする事になり、再度転送手続きを行う必要がある時には、状況に応じて2つの方法があります。
ここでは分かりやすく
前住所地をA
現住所地をB
新住所地をC
と表記して解説していきます。
前提条件として、現在前住所地Aから現住所地Bに郵便物の転送サービスを行っていて、これから現住所地Bから新住所地Cに転居する予定です。
1つ目の方法、前住所地Aから新住所地Cへの郵便物の転送手続きを行う
この場合には、前住所地Aから新住所地をCへの転送手続きを行います。
この手続きを行うことで、現在利用している前住所地Aから現住所地Bへの転送手続きを上書きする事になります。
現住所地Bへの住所変更手続きが進んでおらず、現住所地Bに届く郵便物が殆ど無い、又は少ない場合には、この方法が良いでしょう。
2つ目の方法、現住所地Bから新住所地Cへの郵便物の転送手続きを行う
この場合には現住所地Bから新住所地Cへの郵便物の転送手続きを行います。
この手続きを行うことで、旧住所地Aに届いた郵便物も現住所地Bに届いた郵便物も新住所地Cへ転送されます。
但し、この方法は郵便局を経由して郵便物を転送していくので、転送される数が多くなる程、手元に届くのに時間が掛かります。
この方法は、旧住所地A現住所地Bのどちらにも沢山の郵便物が届く場合に利用すると良いでしょう。
転送手続きは土日祝日でも可能?

転送手続きの方法によって土日祝の対応が異なります。
それぞれの方法にについて解説していきます。
窓口での転送手続き
郵便局が開いていれば土日祝も対応は可能です。
但し、郵便局によって窓口の対応時間が異なるので、大きな郵便局で土日祝も対応してくれる所もあれば、お休みの所もあります。
行く前にホームページから行く予定の郵便局の営業時間を確認すると良いと思います。
転居届けのハガキ
土日祝にハガキを投函できます。
そして、届き次第対応して頂けます。
インターネット
土日祝も申し込む事ができます。
代理人の手続きは可能なの?
転送手続きは代理人でも手続きは可能です。
窓口で転送手続きを行う場合には、転送者の旧住所地が確認できる身分証明書と、提出者となる代理人の身分証明書の2点が必要です。
また、転居届けのハガキやインターネットを使った転送手続きでは、代理人が代行する事に伴い必要となる証明書や委任状はありません。
転居の事実確認について
ここまで解説してきたように郵便物の転送手続きは、その気になれば悪意のある第3者が本人になりすまして転送手続きを行う事が出来ます。
しかし、そんな事を嫌がらせやイタズラでされては大変な事になります。
そこで、郵便局では本人以外が代理をして郵便物の転送手続きが行われた際には、旧住所地又は新住所地のどちらかに郵便局員が訪問して転居の事実確認が行われます。
さいごに
全ての住所変更を済ませたつもりでも、うっかり忘れてしまう事もあります。
そのため、引越しに伴う郵便物の転送手続きは、簡単な手続きで済ませる事ができるので、やっておいた方が良いでしょう。
もし郵便物の転送手続きで戸惑っても、ここで解説した内容を確認しながら進めれば、きっとスムーズに手続きを行えますので安心して手続きに臨んで下さい。
因みに、運送会社のヤマト運輸でも同様の宅急便転送サービスを行っています。
必要な方はヤマト運輸のホームページ(http://www.kuronekoyamato.co.jp/smp/tenkyo/tenkyo.html)から手続きを行うと良いでしょう。
引っ越しのためにある引越し業者に見積もりを取ったら73,300円でした。
高いんじゃないかと思って
あやうく31,300円も損するところだったんです。
複数の業者に見積もりを取ることで安い業者を見つけることができました。
見積もりの手間を省くなら「
利用時間は1分程度で利用料は無料になります。
SUUMOは一部上場企業のリクルートが運営しているサイトで、電話登録が不要で迷惑電話が来ないのも安心です。
引越し料金で損したくない方は是非こちらをご覧ください。
>>>あなたに合った最安値の引越し業者を調べてみる(無料)<<<